小説「宮本武蔵」8巻 感想
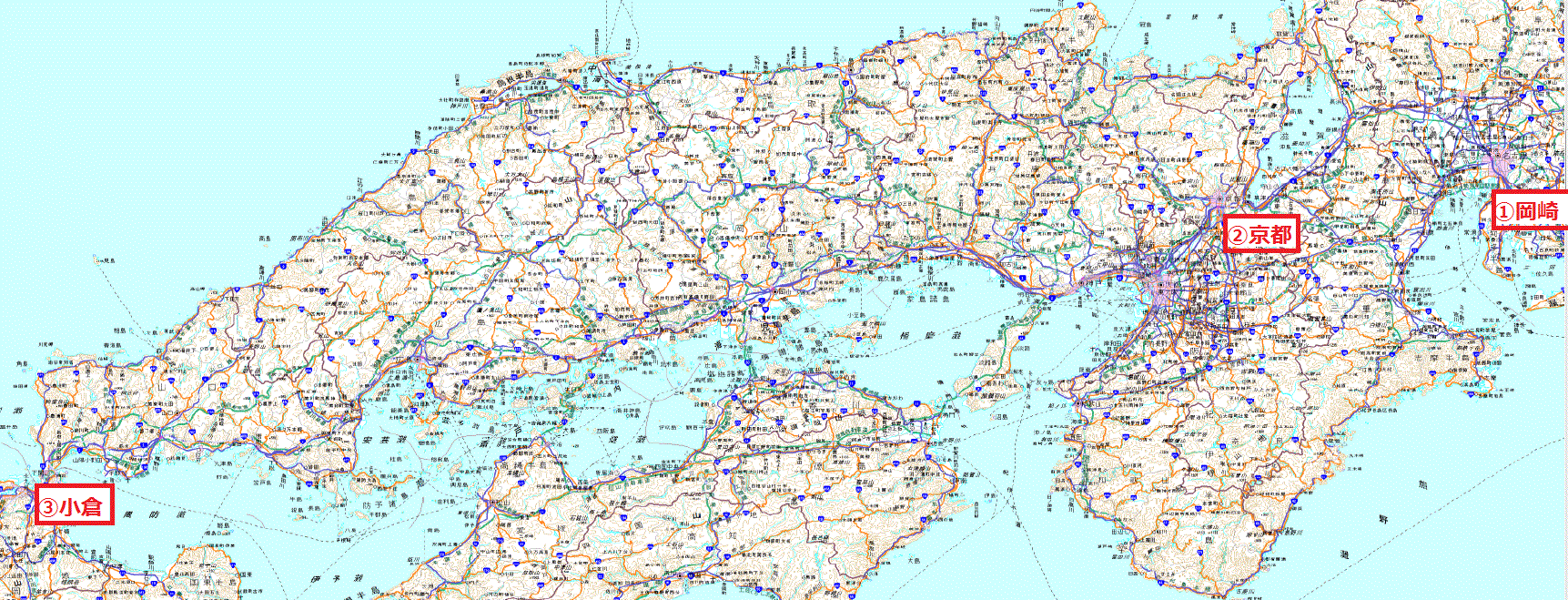
雑記
クリスマスと大晦日の間の静けさ!真夜中に雪がシンシンと降るような感じがあります。
 |
宮本武蔵(八) (吉川英治歴史時代文庫) (1989/12/26) 吉川 英治 |
8巻
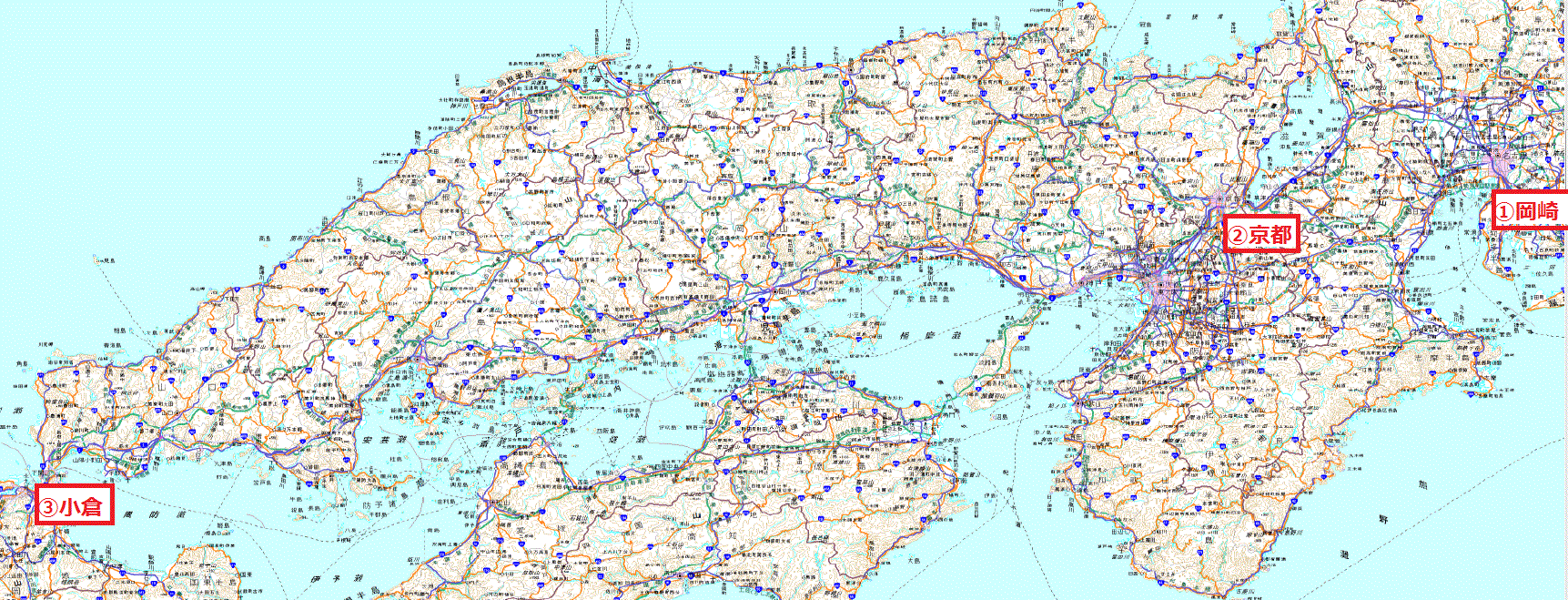 遂に最終巻です。しかし、最終巻=武蔵の死というのではなく、佐々木小次郎との決闘で物語は終わっています。
遂に最終巻です。しかし、最終巻=武蔵の死というのではなく、佐々木小次郎との決闘で物語は終わっています。
武蔵は、①岡崎の町の中で暮らしていましたが自分の道がわからなくなって、愚堂和尚について②京都へ行きます。そして佐々木小次郎との決着をつけるため、舟で③小倉へ行き、そこで多くの知己の人たちと挨拶をかわし、巌流島(舟島)へ渡ります。
これまで多くの達人と出会い、多くの経験を為して、多くの人にその力を認められている武蔵ですが、それでもまだ自分の道を確信することができず、迷い続けているようでした。
「なさんとして、何もできないのである。にっちもさっちも行かない空間に縛られて、果てもないここちがする。」
何をすればいいのか、何をどうすれば自分は救われるのか、この苦しみの道を歩むことは本当に正しい道なのか?などの疑問が湧いて止まらなかったのでしょう。だから、自分ではどうすることもできず、愚堂和尚に教えを乞い願ったのでしょうね。
そして、和尚は武蔵の周りに「円」を描きます。その意味は、
「自己も円、天地も円。二つのものではありえない。一つである」
そう、これはまさに、アートマンとブラフマンが同一のものであることを悟る「梵我一如」の観念です。あまり詳しくはないのですが、仏教での「悟り」とはこの状態を心の奥底から強く知ることなんじゃないでしょうか。(アートマンとブラフマンは正確には仏教用語ではないようですが)
武蔵の精神から迷いが消えます。そして、周りの人たちの望みもあって、遂に佐々木小次郎との決着をつけることになります。
小次郎との決戦前に、武蔵の長い旅路で出会った多くの人と再会したり別れの挨拶をするのですが、この、裸一貫で村から出てきた武蔵にも多くの味方がつき、多くの情けを得ながら旅を続けてきたのだという、長い旅路の総括のような雰囲気があってかなり「終わり」の感じをひしひしと受けましたよ。
例えば、又八や明美、城太郎、お通、おばば、伊織など。彼らも武蔵と同様に迷いの道を歩んでいましたが、収まるべき場所をそれぞれ見つけたようで、後はただ武蔵のみ。佐々木小次郎も最初は細川家に仕えることはそれほど良しとはしてなかったようですが、今では多くの弟子を引き連れて、いるべき場所にいるようでした。
多くの人から応援されるのは佐々木小次郎も一緒で、小倉城で剣の師範になっていたのでその関係者や、親類等。しかし小次郎は世間の情けを感じている武蔵と違って、「自己しか恃むものはない」と思っていたようです。ここに武蔵と小次郎の違いがあり、作者の吉川英治さんがこの物語を通して書きたかったことが示唆されているように思えます。
武蔵と小次郎との決闘。その勝敗を分けたのは、
「小次郎が信じていたものは技や力の剣であり、武蔵の信じていたものは精神の剣であった」
とのことでした。思えば、武蔵の言う強さとは、「人としての強さ全体」であり、小次郎の言う強さとは「剣士として相手を圧倒する武力」のことを指していたのでしょう。剣士としての強さもやはり心の強さは必要です、が、武蔵の心の強さとはもっともっと世界を巨視的に見た、世界の根底に在る共通の観念を知り、それに順ずること。
世間には多くの人が生活しています。侍、農民、町民など。彼らは身分が異なっていたりしますが、彼らも彼らなりの努力や生き方をして、それぞれが必死に生きています。自分ひとりが頑張っていて、自分ひとりでやっていけるというのではなく、自分や世間が接触しあって多くのものを生み出していく。個人は天地があってこそ生きていける、天地と同一のものである、というのが武蔵の得た答えなのでしょうね。
確かに剣の技術では小次郎のほうが上回っていたのかもしれません。しかし、剣の技術だけでない、あらゆる「道」全体を視野に入れた武蔵が剣だけでは収まらない強さを得たことによって、小次郎に勝てたのだろうと、この小説では言っているのだと思います。
波にまかせて、泳ぎ上手に、雑魚は歌い雑魚は躍る。けれど、誰か知ろう、百尺下の水の心を。水のふかさを。
魚歌水心、武蔵について多くの言説が流れても、その心の奥底は知れない。この深く、そして澄み切った蒼穹なる色をした水の底を。
1巻
2巻
3巻
4巻
5巻
6巻
7巻