蒲団・重右衛門の最後 感想
蒲団・重右衛門の最後 作 田山花袋
明治時代に勃興した自然主義文学の、その代表作だとも言われる田山花袋著作の「蒲団」と「重右衛門の最後」についての感想を書いていきますよ。
自然主義文学というのは、「事実をありのままに記録する」というのが定義のようで、作者が言いたいことを表すために物語を作っていくような作り方の逆のような感じなのかな?そして、物事を鳥のように俯瞰的に見るのではなく、地べたから見ていくということなのでしょうかね。
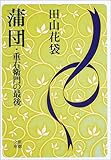 |
蒲団・重右衛門の最後 (新潮文庫) (1952/03) 田山 花袋 |
蒲団
主人公の時雄は、30代の中年男性です。妻も子供もいますが、妻は子供にかまって子供は妻にかまっており、自分の家庭での存在感は少なめ。そして、仕事もあまりパッとしないものであり、自分の仕事に対して満足はしていないようです。この年になると、世間から落ちつきを求められるようになりますが、時雄はまだ性欲などの欲求を持っており、女性関係での新たな事件を心の奥底では望んでいます。
芳子は、典型的な明治の女学生のようで、江戸時代の女性よりも行動的であり男性と対等でいることに遠慮はありません。明治の女学生の、長所と短所の両方を受け継いでいるというわけですね。
あらすじは、上記のような性質である時雄が、芳子が家にやってくることでロマンスが生まれるのかと思っていたけど、芳子に好きな男性が出来ていたので、その機会は失われてしまった…、という感じでしょうかね。
時雄は芳子の「明治の女学生らしさ」を奨励していましたが、芳子が好きな男性が出来たことで、その無遠慮な様子に顔をしかめてしまっています。昔(江戸時代辺り)では、「こういう挙動をしているのなら、相手は自分を好いているのだろう」と判別できるような女性の行動がありましたが、明治になるとその行動も異なってきて、女性が男性と親密な行動をとっても、それは友達のような関係であるということを表していたりすることなどがあります。
つまりですね、江戸と明治では、男性と女性との距離感が異なってきているというわけですね。明治時代では江戸時代よりも、女性は恋していない男性にでも近づくようになっており、過去から生きてきた男性にはそこに感覚の齟齬が生じているのです。
それは、「明治の人間」だと自負する時雄も一緒のようで、芳子の行動的であり男性と積極的に親密になろうとする「明治の女学生らしさ」を時雄は好いており、そして芳子の行動は明治らしさの結果なのに時雄は「芳子は自分のことを好いているのではないか?」と勘違いしてしまっているのだと思いますね。
つまり、時雄は明治を理解しているつもりだったのに、本能の面では100%受け入れるというのはできていなくて、だから、「芳子は自分を裏切った!欺いた!」という感情が出てきてしまったのでしょうね。
まあ、でも…、現代の人間である私から見ても、芳子とその彼氏である田中にはいらつきましたよ。何と言うかね、二人とも言い訳がましくて悲劇のヒーロー・ヒロインぶっていて、「自分が悪いんじゃなくて他人・社会が悪い!」というような思想が醸し出されていてですね…。
二人の愛情は本物のようなんですが、恋は盲目と言いますか、自由は責任と共に存在することを理解していないと言うか、将来熱が冷めたら家庭が荒れそうな刹那的に生きているというようなことを感じられました、個人的に。
でも、そういうわがままこそが、自然主義の結果でもあるのかもしれませんね。
この「蒲団」についての最近の感想を少しネット上で読みましたが、人々は「やったかやってないかが、そんなに重要か?」と思っているようです。個人的には、そこは重要です。ヤルことを言い換えれば、「一線を越える」と言い、文字通りその行為は男女の関係の重要な一線を越える行為でしょう。
作中で時雄はこのようなことを言っていました。
「古人が女子の節操を戒めたのは女子の自由を束縛するのではなく、実は女子の独立・自由を保護するためである。一度そこを許せば、女子の自由は全く破られる」
つまり、そういう行為には自分にも相手にも大きな責任・変革が生じるのですな。そのような重大な行為を、芳子と田中は安易で刹那的な感情で破ったところに、二人の罪があると私は思います。
私たちが生きる現代では、簡単にヤルような人間が多いですが、何かしらの弊害が出てくる確率はかなり高いと私は思います。最近は、「セックスは汚らわしい」と思う男性の割合が増えているようです。フリーセックスの弊害はそこにあると思います。「蒲団」の感想と大きく外れてしまっていますが。
この「蒲団」という小説は、時雄の欲深く汚い欲望が赤裸々に描かれており、その滑稽さや哀れさに読者は少なからず笑いを誘われるのでしょうが、ラストは少し切ないものだと思います。
時雄が持っていた芳子への希望だとか処女性は失われ、自分の認識と感情も含めて全ては過ぎ去ってしまい、ロマンスを期待していたのに今までどおりの夢の無い現実に戻ってしまったという結果になってしまったようです…。
あのときの感情は本物だった!のでしょうが、今はもう、時代にも取り残されて物語の主人公になりえない。そんな、幸福にも不幸にもならない煩悶の中を生きていく羽目になる。それが、現実なのでしょうかね。
重右衛門の最後
あらすじは、東京人(多分)である主人公の富山が、信州から東京にやってきた人と友達になり、その故郷の美しさを聞いて興味を持ち、その故郷に行きます。その信州の山中にある故郷では、重右衛門という厄介者が村で放火を行っており、最終的には村人が重右衛門を殺すことになります。
全体的に見れば、美しい自然の中で生まれ、生まれつきの不具による自然な気持ちや感情の成長、そして村人の自然な感情からの自然な結果になるというように、あるがままの状態・現象・結果を客観的に見て評価・考察した小説だと私は思います。
「自然らしさ」を出すために、まずは景色の描写がありましたが、漢文のような空や山々などを表した言葉の数々は中々レベルの高いもので、信州の田舎の清廉な空気を読者も感じることが出来るほどです。
自然の考察の題材となる重右衛門の過去などはほぼ全て語られており、彼が非道な人間になってしまった理由もよく理解できます。だからこそ、そこに考察の余地があるわけで、主人公の富山は「重右衛門は悪人か?」というようなことを考えます。
重右衛門は自然に与えられた性質・環境で生きてきたので、そのようになった責任はそこにあるのだとも言えます。そして、重右衛門が生きて殺されたのは、決して無意味ではなく、百姓として生きた人間や商人として生きた人間のように、世の中から与えられた役割を果たした一人だとも考えます。
個人的には、少々主人公は重右衛門の肩を持ちすぎな気がしましたね。重右衛門が非道な人間になったのにはやはり理由がありましたが、でもやっぱり彼に傷つけられた村人達の気持ちも考えれば、重右衛門は殺されるべくして殺された人間だと思いますよ。
過去を考えれば哀れではありますが、悪人の全てが生まれつきの悪魔でもないので、重右衛門は「悪人」だとして裁いたほうが社会として正しいのではないかと私は思いますね。絶対悪は存在しないと言っても良いから、見かけ上の悪でもやはりそれは社会的に悪であり、本質なのだろうと。